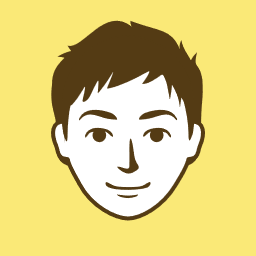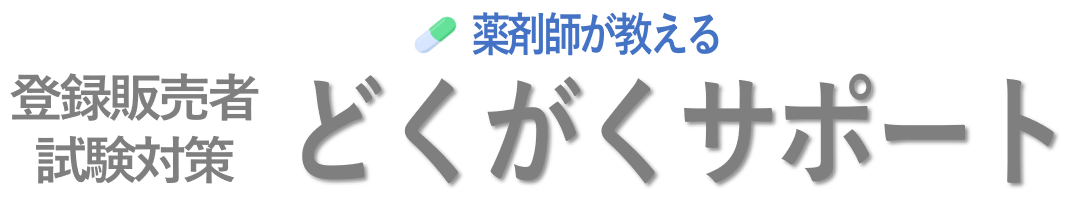登録販売者試験の解説とポイントを過去問題にフォーカスして記載していきます。
厚生労働省の試験問題作成の手引きを基に分かり易い内容に変えて解説しています。
過去問題から作成したポイントテストもありますので、
是非解いて見てくださいね。
独学で学ばれている方も含め問題なく解けることが実感できるかと思います。
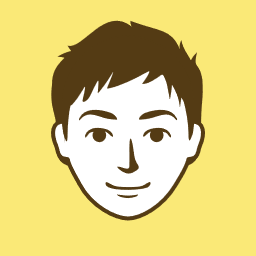
また第3章全体のポイントについては、第3章-1日目:Ⅰ-①:かぜ薬をご覧ください。
1 漢方処方製剤
1)漢方の特徴・漢方薬使用における基本的な考え方
漢方医学は古来に中国から伝わり、日本で発展してきた日本の伝統医学であり、現代中国で利用されている中医学や、韓国伝統医学の韓医学とは区別されています。
漢方処方製剤の多くは、処方に基づく生薬混合物の浸出液を濃縮して調製された乾燥エキス製剤を散剤などに加工して市販されています。
漢方薬を使用する場合、漢方独自の病態認識である「証」に基づいて用いることが、有効性および安全性を確保するために重要です。
漢方の病態認識には虚実、陰陽、気血水、五臓などがあります。
「証」が合わないと、効果が得られないばかりでなく、副作用を生じやすくなります。
一般用医薬品の場合、「証」という漢方の専門用語を使用することを避け、「しばり」(使用制限)として記載が行われています。
| 証に関する具体例 | ||
| 証 | しばり(使用制限) | |
| 虚実 | 体力に関するもの。「体力中程度で」など | |
| 陰陽 | 陰 | 「疲れやすく冷えやすいものの」など |
| 陽 | 「のぼせぎみで顔色が赤く」など | |
| 五臓 | 脾胃虚弱 | 「胃腸虚弱で」など |
| 肝陽上亢 | 「いらいらして落ち着きのないもの」など | |
| 気血水 | 「口渇があり、尿量が減少するもの」(水毒) | |
| 「皮膚の色つやが悪く」(血虚)など | ||
漢方処方製剤は体質改善を目的に比較的長期間(一ヵ月程度)服用されることがあります。
「漢方薬は作用が穏やかで、副作用が少ない」といった誤った認識がなされていることがありますが、漢方処方製剤においても間質性肺炎や肝機能障害のような重篤な副作用が起きることがあります。
なお、漢方処方製剤は用法用量に適用年齢の下限が設けられていない場合であっても、生後3ヶ月未満の乳児には使用しないこととされています。
ポイントテスト1
下記問題を正誤で答えよ(回答は下)
(1)漢方薬は、現代中国で利用されている中医学に基づく薬剤のことである。
(2)漢方処方製剤を利用する場合、患者の「証」に合った漢方処方が選択されれば効果が期待できるが、合わないものが選択されたとしても、副作用を生じにくいとされている。
(3)漢方処方製剤は、症状の原因となる体質の改善を主眼としているものが多く、比較的長期間 (1ヶ月位)継続して服用されることがある。
(4)用法用量において適用年齢の下限が設けられていないので、生後1ヶ月未満の乳児にも使用してもよい。
回答と解説
ポイントテスト1
(1)×:漢方薬は中医学、韓医学と異なる。
(2)×:「証」が合わないものは副作用を生じやすい。
(3)〇
(4)×:適用年齢の下限がない場合、生後3ヶ月未満の乳児には使用しないこととされている。
2)代表的な漢方処方製剤、適用となる症状・体質、主な副作用
漢方処方製剤
- 黄連解毒湯
- 防已黄耆湯
- 防風通聖散
- 大柴胡湯
- 清上防風湯
カンゾウ,マオウ,ダイオウを含む場合
それぞれ㋕,㋮,㋟で記載
(a)黄連解毒湯
体力中等度以上で、のぼせぎみで顔色赤く、いらいらして落ち着かない傾向のあるものの鼻出血、不眠症、神経症、胃炎、二日酔い、血の道症、めまい、動悸、更年期障害、湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ、口内炎に適す。
まれに重篤な副作用として肝機能障害、間質性肺炎、腸間膜静脈硬化症が起こる。
(b) 防已黄耆湯 ㋕
体力中等度以下で、疲れやすく、汗のかきやすい傾向があるものの肥満に伴う関節の腫れや痛み、むくみ、多汗症、肥満症(水ぶとり)に適す。
構成生薬としてカンゾウを含む。
まれに重篤な副作用として肝機能障害、間質性肺炎、偽アルドステロン症が起こることが知られている。
(c) 防風通聖散 ㋕㋮㋟
体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症(副鼻腔炎)、湿疹・皮膚炎、ふきでもの、肥満症に適す。また小児への適用はない。
構成生薬としてカンゾウ、マオウ、ダイオウを含む。
まれに重篤な副作用として肝機能障害、間質性肺炎、偽アルドステロン症、腸間膜静脈硬化症が起こることが知られている。
(d) 大柴胡湯 ㋟
体力が充実して、脇腹からみぞおちあたりにかけて苦しく、便秘の傾向があるものの胃炎、常習便秘、高血圧や肥満に伴う肩こり・頭痛・便秘、神経症、肥満症に適す。
構成生薬としてダイオウを含む。
まれに重篤な副作用として肝機能障害、間質性肺炎が起こることが知られている。
(e)清上防風湯 ㋕
体力中等度以上で、赤ら顔でときにのぼせがあるもののにきび、顔面・頭部の湿疹・皮膚炎、赤鼻(酒さ)に適す
構成生薬としてカンゾウを含む。
まれに重篤な副作用として肝機能障害、偽アルドステロン症、腸間膜静脈硬化症が起こることが知られている。
ポイントテスト2
第1欄の記述は、マオウを含む漢方処方製剤に関するものである。該当する漢方処方製剤は第2欄のどれか。
第1欄
体力が充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症(副鼻腔炎)、湿疹・皮膚炎、ふきでもの、肥満症に適すとされるが、体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)、胃腸が弱く下痢しやすい人、発汗傾向の著しい人では、激しい腹痛に伴う下痢等の副作用が現れやすい等、不向きとされる。
第2欄
1 黄連解毒湯
2 防風通聖散
3 清上防風湯
4 防已黄耆湯
5 大柴胡湯
回答と解説
ポイントテスト2
正解は2
マオウを含む段階で、防風通聖散ですが、その他に、「腹部に皮下脂肪が多く」「便秘がち」「肥満症、蓄膿症」
などがキーワードとなる。防風通聖散にはカンゾウ、マオウ、ダイオウを含む。
3)相互作用
漢方処方を構成する生薬には、複数の処方で共通しているものもあり、同じ生薬を含む漢方処方製剤が併用された場合、作用が強く現れたり副作用を生じやすくなるおそれがあります。
小柴胡湯とインターフェロン製剤の相互作用のように、医療用医薬品との相互作用も知られています。
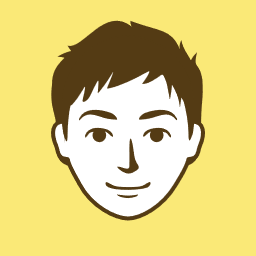
また、生薬成分は効果が標榜または暗示されなければ、食品(ハーブなど)として流通が可能なものもあるため注意が必要です。
ポイントテスト3
下記問題を正誤で答えよ(回答は下)
(1)漢方処方を構成する生薬には、複数の処方で共通しているものもあり、同じ生薬を含む漢方処方製剤が併用された場合、作用が強く現れたり、副作用を生じやすくなるおそれがある。
(2)小柴胡湯とインターフェロン製剤との併用は、相互作用を起こすため、避ける必要がある。
(3)生薬製剤に配合される生薬成分は、医薬品的な効能効果が標榜又は暗示されていなければ、食品(ハーブなど)として流通することが可能なものもある。
回答と解説
ポイントテスト3
(1)〇
(2)〇
(3)〇
2 生薬製剤
生薬製剤は、生薬成分を組み合わせて配合された医薬品です。
漢方処方製剤のように体質や症状に適した配合を選択するわけではなく、個々の生薬成分の薬理作用を主に考えて配合されるものであり、西洋医学的な基調の上に立つものです。
1)代表的な生薬成分、主な副作用
生薬は、湿気及び虫害などを避けて保存が必要です。
- ブシ
- カッコン
- サイコ
- ボウフウ
- ショウマ
- ブクリョウ
- レンギョウ
- サンザシ
(a) ブシ
キンポウゲ科のハナトリカブト又はオクトリカブトの塊根を減毒加工して製したものを基原とする生薬
心筋の収縮力を高めて血液循環を改善する作用を持つ。血行促進による利尿作用、鎮痛作用も示す。
アスピリン等と異なり、プロスタグランジンを抑えないことから、胃腸障害等の副作用は示さない。
ブシは生のままでは毒性が高いことから、毒性を減らし有用な作用を保持する処理を施している。
(b) カッコン
マメ科のクズの周皮を除いた根を基原とする生薬
解熱、鎮痙の作用を期待して用いられる。
(c) サイコ
セリ科のミシマサイコの根を基原とする生薬
抗炎症、鎮痛、解熱の作用を期待して用いられる。
(d) ボウフウ
セリ科のSaposhnikovia divaricata Schischkinの根及び根茎を基原とする生薬
発汗、解熱、鎮痛、鎮痙の作用を期待して用いられる。
(e) ショウマ
キンポウゲ科のCimicifuga dahurica Maximowicz、Cimicifuga heracleifolia Komarov、Cimicifuga foetida Linné またはサラシナショウマの根茎を基原とする生薬
発汗、解熱、解毒、消炎の作用を期待して用いられる。
(f) ブクリョウ
サルノコシカケ科のマツホドの菌核で、通例、外層をほとんど除いたものを基原とする生薬
利尿、健胃、鎮静の作用を期待して用いられる。
(g) レンギョウ
モクセイ科のレンギョウの果実を基原とする生薬
鎮痛、抗菌の作用を期待して用いられる。
(h) サンザシ
バラ科のサンザシ又はオオミサンザシの偽果をそのまま、又は縦切若しくは横切したものを基原とする生薬
健胃、消化促進の作用を期待して用いられる。
同属植物であるセイヨウサンザシの葉は、血行促進、強心等の作用を期待して用いられる。
ポイントテスト4
下記問題を正誤で答えよ(回答は下)
(1)ブシは、キンポウゲ科のハナトリカブト又はオクトリカブトの塊根を減毒加工して製したものを基原とする生薬で、心筋の収縮力を高めて血液循環を改善する作用を持つ。
(2)サイコは、マメ科のクズの周皮を除いた根を基原とする生薬で、解熱、鎮痙等の作用を期待して用いられる。
(3)ブクリョウは、サルノコシカケ科のマツホドの菌核で、通例、外層をほとんど除いたものを基原とする生薬で、利尿、健胃、鎮静等の作用を期待して用いられる。
(4)サンザシは、モクセイ科のレンギョウの果実を基原とする生薬で、 鎮痛、抗菌等の作用を期待して用いられる。
(5) 生薬製剤は、生薬成分を組み合せて配合された医薬品で、漢方処方製剤と同様に、使用する人の体質や症状その他の状態に適した配合を選択するという考え方に基づくものである。
回答と解説
ポイントテスト4
(1)〇
(2)×:サイコではなく、カッコン。
(3)〇
(4)×:サンザシではなく、レンギョウ。
(5)×:漢方処方製剤と異なり、生薬製剤は個々の薬理作用を主に考えて、配合される。
2)相互作用、受診勧奨
【相互作用】
生薬成分には、複数の製品で共通するものも存在し、また食品として流通するものもあるため、同成分の使用により、作用の増強や副作用が発現する可能性があります。
【受診勧奨】
生薬製剤も、漢方処方製剤と同様、体質の改善を主眼として、比較的長期間継続して服用されることがあります。
「生薬製剤はすべからく作用が緩やかで、副作用が少ない」などという誤った認識に注意が必要です。
センソ(強心薬の項を参照)のように少量で強い作用を示す生薬もあります。
ページ内薬剤一覧
| 漢方、生薬成分 | ||||
| 分類 | 成分名 | 作用・効果 | ||
| 漢方処方製剤 | 黄連解毒湯 | いらいらして落ち着かない傾向のあるものの鼻出血、二日酔い | ||
| 防已黄耆湯 ㋕ | 肥満(水ぶとり) | |||
| 防風通聖散 ㋕㋮㋟ | 腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちな肥満症、蓄膿症 | |||
| 大柴胡湯 ㋟ | 脇腹からみぞおちにかけて苦しく、便秘の傾向がある肥満症 | |||
| 清上防風湯 ㋕ | 赤鼻 | |||
| 生薬成分 | ブシ | キンポウゲ科 血液循環を改善、利尿作用、鎮痛作用 |
||
| カッコン | マメ科 解熱、鎮痙 |
|||
| サイコ | セリ科 抗炎症、鎮痛 |
|||
| ボウフウ | セリ科 発汗、解熱、鎮痛、鎮痙 |
|||
| ショウマ | キンポウゲ科 発汗、解熱、解毒、消炎 |
|||
| ブクリョウ | サルノコシカケ科 利尿、健胃、鎮静 |
|||
| レンギョウ | モクセイ科 鎮痛、抗菌 |
|||
| サンザシ | バラ科 健胃、消化促進 |
|||